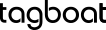アートフェアに見る欧州のトレンド
10月に開催された欧州の二大アートフェア(フリーズ・ロンドン、バーゼル・パリ)を見て感じた大きなトレンドについてお話をしたいと思う。
最新の作品の方向性といったことについては特に目新しいものがあるわけではなく、何かブームのようなものは感じられなかった。
過去の長い歴史の上に現在のアートがあることを改めて感じさせられ、欧州のアートというものが時間の蓄積を経て今に至ることを痛感させられた。
競争の激化
まさに欧州のアート市場は群雄割拠の時代であると感じた。
若手のギャラリーがどんどん増えており、大手のメガギャラリーがうかうかできない状況になっている。
クオリティの高いアートフェアに出展するためにそれぞれがしのぎを削っているのだ。
同時にアーティストの数が増えて多様化しているので、アートフェア自体が他にはない差別化された作品を見せる競争の場となっている。
欧州とは逆に、日本の場合はアートフェアの立ち位置が「行商的な売買の場」と化している。
自社で展覧会をしてもはあまり人が来ないギャラリーが、アートフェアに来場するコレクターに作品を売ることを目的として出展をしているからだ。
一方、欧州では目の前の売買を目的とするよりも、アートフェアをより長期的な視点でビジネス活用している点が特徴的である。
アートフェアを一押しのアーティストの新作を見せる「お披露目の場」と位置付けており、来場者に新しい作品のコンセプトの理解を深めてもらうプロモーションの場となっているのだ。
アーティストの知名度を強化するにはアートフェアは格好の場であるため、なぜこの作家がすごいのかをギャラリーが会場で推奨しまくっている状況である。
将来的に価値が高くなるすごい作品であることを、コンセプトの独特さや面白さで競争させているため、特に言語が多様化する欧州ではわかりにくい説明はご法度であり、理解されやすい表現方法に工夫をしていることを感じた。
フェアの時期に合わせて、ギャラリーがアーティストをメディアに露出する競争の激化はやむことがないように思われる。
作品の傾向
作品の傾向にも、少しだけ目を向けてみよう。
ひとつは、ベネチアビエンナーレにも見られたことであるが、作家が生まれた故郷の土着の文化を現代アート作品に作り直して伝える「古典回帰」的な作品が多かったことだ。
インターナショナルなギャラリーは自国のアーティストだけではなく、様々な国から優秀なアーティストを引っ張り込んでプロモーションしているが、その多様化が進んだ結果として、作家の育った文化を過去の歴史からひも解いて見せていく手法が増えたように感じた。
その傾向にもとづいているのかどうかは分からないが、文字が作品の中に入っている作品も増えているように感じた。
欧州なのでアルファベットの文字が作品に多用されているのは確かであるが、それ以外にも様々な言語が散りばめられた作品が増えている。
これまでのファインアートの常識では、絵画などの平面作品に文字を入れてしまうとそれを読むだけ強い意味を持つので避けられてきたことなのだが、逆に文字そのものをアートとしたり多様性がより広がっているようだ。
それだけでなく、欧州であるためファッションとの繋がりを意識させるようなデザイン性の高さを感じる抽象画は多い。
ファッションとのコラボが当たり前になっている時代を反映させたものだ。
同時に有名ブランドネームとの関係性を皮肉な意味で批判するような作品も見られた。
そのような世相を強く批判するような風刺画は当たり前になってきている。
日本では政治や体制に対する風刺画をアートフェアで見ることは少ないが、欧州ではある程度それがないと不思議なくらいだ。
また、写実絵画やオーソドックスな油絵などの表現は普通にあるが、美人画などコンセプトがはっきりしないものは存在せず、コンセプトの違いや見せ方に力を入れている
日本的なアニメ、キャラクターは、それ自体を揶揄する対象として作品が作られることはあってもメインの表現方法としての作品は見ることがなかった。
さらには、昨年から国内のアートフェアでも散見されたNFTアートのブームはまったく見られなかった。
デジタルアートとしての映像作品はあってもディスプレイ付きで販売されており、いかにもNFTアートであることを強調した作品であったり、NFTに特化したブースも存在しなかった。
おそらく、アートの歴史が長い欧州では、NFTは従来のファインアートとは別物としての理解なのだろう。NFTとアートとを一緒くたにされずに、切り離された独自のカルチャーとして進化していくのだろうと推察される。
全体として、歴史が長い欧州のアートフェアは、流行りのものを見せたり著名なアーティストを売る場ではなくて、長期的な視野を持ってコレクターにこれから来る新しいアーティストの作品を紹介して知ってもらい買ってもらう場として機能している場であることを強く感じたし、このトレンドがいつか日本にも浸透してほしいと思う。