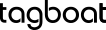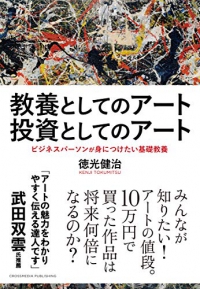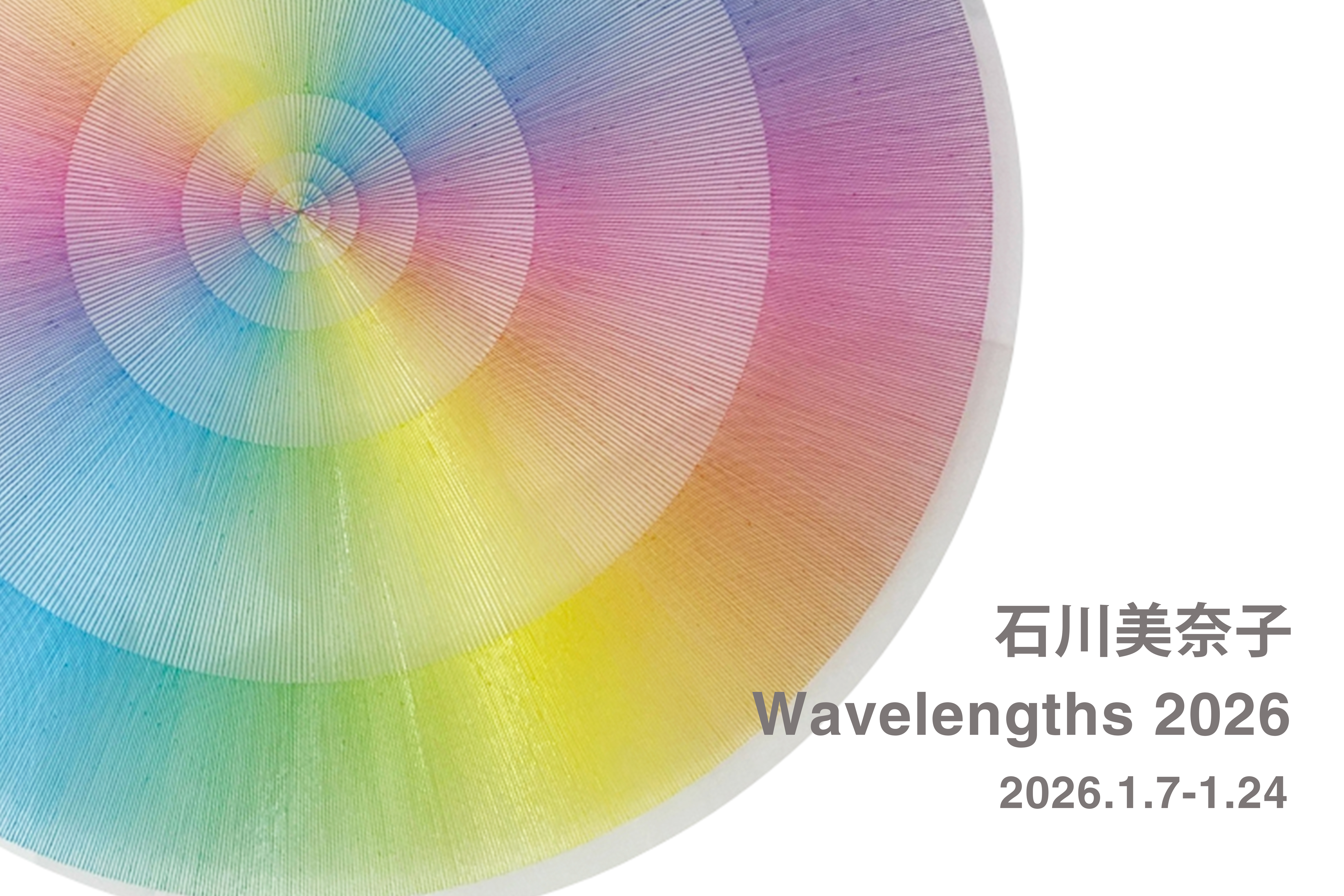アーティストがアート市場を変える
アーティストを目指す人の数が、今、確実に増えている。
それは趣味や副業という意味にとどまらず、「本業としてのアート」に真剣に取り組もうとする人が、年齢や職業を問わずに増加しているのである。
実際に、タグボートが主催する「Independent Tokyo」では、出展希望者の応募が年々増え続けており、近年では募集締切を待たずに定員が埋まるようになった。
これはアートのプロとして活躍したいと考える人が、それだけ多くなっているという現実を示している。
その背景には、社会の構造的な変化がある。
コロナ禍によって在宅勤務が増え、人々の時間の使い方が変わった。
さらにAIの進化により、事務的・定型的な業務の多くが自動化されつつあり、人間にしかできない仕事、すなわち「創造性」がますます価値を持つ時代となった。
だが、その「創造性」すらもAIが模倣できるようになった今、人間にしかできない表現とは何かがあらためて問われている。
その問いに真正面から向き合い、答えを作品として提示する職業こそが、アーティストなのである。
現代アートとは、技術や知識の積み重ねだけでは到達できない、唯一無二の視点や哲学を形にする行為である。
他者の真似ではなく、自分自身の感性にしかたどり着けない世界。誰もができることではない「発明」を求められる、きわめて高度な創造行為だ。
しかしながら、アーティストという職業が現実的に成り立つかというと、話はそう簡単ではない。
ここで立ちはだかるのが、日本のアートマーケットの構造的な課題である。
現在、日本のアート市場の規模は先進国の中でもきわめて小さい。一人あたりの年間アート購入額はアメリカ、ヨーロッパ、中国と比べても圧倒的に低く、国内市場だけでは十分な収益を得られないアーティストが大半である。
コロナ禍で一時的に活気を帯びたアート市場も、現在は縮小傾向にあり、作品が思うように売れない「冬の時代」が訪れている。
この現実を正面から見つめずに、「アートは素晴らしい」「夢があれば大丈夫」といった幻想を抱いたままでは、挫折する人が増える一方である。
現実は厳しい。だが、その中でも可能性は確実に存在する。
鍵となるのは、「市場を選ぶ」という視点である。
国内だけを相手にするのではなく、グローバル市場や別業界との接点を持つことが、生存戦略として重要になる。
たとえば、ファッション、音楽、デザイン、ゲーム、アニメーションなどの分野では、日本発のコンテンツが世界的に評価されており、その中に現代アートが入り込む余地は大いにある。
そのためには、アーティスト自身が、自らの作品をどの文脈で発信するかを考え、広い意味での「市場選定」をする必要がある。
単に作品を作るだけでなく、どこで、誰に、どう見せるか。SNSでの発信、オンラインギャラリーの活用、クラウドファンディング、ポップアップイベントの実施など、自分の活動をマルチチャネルで展開することが、今の時代の必須条件となっている。
かつては、公募団体展への出展や、銀座の貸しギャラリーでの個展がキャリア形成の王道とされていた。
だが、現代のギャラリストやコレクターがそうした場を巡回して新人を発掘するような時代ではない。
むしろ、SNSやポートフォリオサイトでの発信こそが、「第一印象」となり、チャンスへの入り口となっている。
Independent Tokyoでは、こうした現実をふまえ、「展示の場を与える」だけでなく、「勝てる環境を整える」ためのサポートを行っている。
具体的には、「トクミツコンサル」と名付けたセミナーを開催し、展示方法、価格設定、キャプションの書き方、SNS活用術、そしてプロモーション戦略まで、アーティストが自立するための具体的なノウハウを提供している。
もちろん、アートに決まった方程式は存在しない。
だが、何の地図もなく航海に出るよりも、基本的な航海図を持っていた方が、成功にたどり着く確率ははるかに高い。
創作という孤独な作業に没頭するアーティストにとって、社会との接点を戦略的に築くことは、自らの活動を継続可能にするための現実的な武器なのである。
タグボートとしても、そうしたアーティストたちを支えるために、展示機会の提供にとどまらず、販売支援、ブランディング、動画制作、SNS運用のサポートなど、多角的な支援体制を整えていきたい。
才能あるアーティストを早期に発見し、いかに市場に橋渡しできるか。
そのミッションは、今後ますます重要性を増すと考えている。
そしてもう一つ、今後のアート業界全体にとっても鍵となるのが、他業界との融合である。
アートがアートの中だけで完結する時代は終わった。
ファッションブランドとのコラボ、音楽イベントとの連動、ゲームやアニメとのビジュアル連携、NFTなどのデジタルアート領域への展開。
あらゆる分野と自由に交わり、そこでアートならではの視点を提示することが、新しい市場を生む道となる。
アートは本来、もっとも自由な表現であり、もっとも社会と結びつく可能性を持っている。
その自由さと創造性を信じるからこそ、アートを軸にしながら柔軟に展開していくことが、いま最も求められている。
アーティストの挑戦は、単なる自己表現ではない。
社会に対する問いであり、未来への提案である。
厳しい現実の中で、ただ一つの道を切り拓く力を持つのは、創造のエネルギー以外にないのだ。