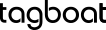

日本のアート市場について語る前に、まずこのコラムの目的を明確にしておきたい。
私たちは日本のアート市場の現状をただ分析するだけではない。
その課題に対して、タグボートがどのように立ち向かい、市場の先兵としてどのような施策を展開しているのか、リアルタイムで報告していく。
その過程は、挑戦の記録であり、成功や失敗も含めた実体験の共有である。厳しい現状認識からスタートし、具体的な解決策を模索することで、日本のアート市場に新たな息吹を吹き込むことが私たちの使命だ。
日本のアートマーケットはここ数年、正直なところ「もどかしい」状況にある。
実際には富裕層の数は増加している。ラグジュアリーブランドや高級不動産が売れ、海外旅行も盛況。それにもかかわらず、アートコレクターの数は一向に増えない。このギャップは一体何なのか。
まず、日本ではアートが「贅沢品」や「特別な趣味」として捉えられていることが多い。
アートに興味を持つ人は多いが、実際に購入に至る人は少数派。これはまるで、美味しそうなケーキをショーウィンドウ越しに眺めるだけで、実際にフォークを手に取る勇気が出ないようなものだ。アートは手の届かない存在として、心理的な壁が立ちはだかっている。
さらに、アートフェアやギャラリーに足を運ぶ人は増えているが、作品を購入する人は全体の5%未満。
これは驚くべき数字だ。多くの人が「見ること」は楽しんでいるのに、「買うこと」への一歩を踏み出せない。
このギャップを埋めるためには、アート購入のハードルを下げ、もっと気軽にアートと向き合える環境を作る必要がある。
「アートは富裕層や専門家のためのもの」という固定観念が根強い日本。
これは、まるで高級ワインが一部のソムリエだけの楽しみと誤解されているのと似ている。
しかし、実際にはアートもワインも、多様な価格帯があり、初心者が楽しめる入り口はたくさん存在する。
心理的ハードルの一つは、価格への不透明感だ。アートフェアやギャラリーで価格が明示されていないことが多く、「値段を聞くのは失礼では?」という日本人特有の気遣いが購買意欲を削ぐ。
この文化的背景は、飲食店でメニューに価格が書かれていないと戸惑う感覚に似ている。透明性を高め、価格についてオープンに語ることで、この壁を少しずつ崩していく必要がある。
また、アート市場は閉鎖的で、初心者が参入しづらい構造になっている。ギャラリーとの強固な関係がなければ、注目作品の購入機会すら得られないことが多い。
これはまるで、常連客だけが知る隠れ家的なバーのようなもので、新規顧客には扉が半分しか開かれていない。私たちは、この扉を大きく開き、誰もが気軽に入れる市場を作りたいと考えている。
「アートは投資になる」というフレーズは魅力的だ。しかし、実際にはそんなに単純な話ではない。
世界の一流ギャラリーが扱うトップアーティストの作品ならリターンの可能性は高いが、それ以外の多くの作品は市場データが不十分で、価格の上下動が読みにくい。
ここで重要なのは、「投資」と「投機」の違いだ。
アートは短期的な価格変動を狙う投機ではなく、長期的に価値が育つ投資として捉えるべきだ。これは、株式市場でのデイトレードと、配当を重視した長期投資の違いに似ている。
アートも、アーティストのキャリアや市場の動向を見極めながら、じっくりと価値を育てる姿勢が求められる。
また、アートを資産価値だけで語るのは、ワインをアルコール度数だけで評価するようなもの。作品がもたらす感動や、美的体験そのものが価値であることを忘れてはならない。
コロナ禍では、旅行や外食が制限されたことで富裕層がアートに目を向け、一時的なバブルが発生した。これは、突如として家庭菜園に目覚める人が増えた現象にも似ている。
しかし、パンデミックの収束とともに消費行動は元に戻り、アート市場も一部では減速傾向にある。
この経験から学べるのは、アート市場の安定した基盤づくりの重要性だ。短期的なブームに頼るのではなく、継続的なコレクター層の育成と市場の多様化が必要である。
アートフェアは多様な作品に触れる貴重な機会だが、課題も多い。特に、ブース出展費用の高さが中小ギャラリーにとって大きな負担となり、収益性の確保が難しい。
また、価格表示の不透明さが来場者の購買意欲を削ぐ要因となっている。
価格を明示し、気軽に質問できる雰囲気づくりが求められる。これは、カフェでメニューに「本日のおすすめ」が書かれていると頼みやすくなる心理と同じだ。
また、アートフェア自体を「買う場」だけでなく、「体験する場」として再設計することも重要である。
アート市場の持続的な成長には、新たなコレクター層の開拓が不可欠である。そのためには、教育、エンターテインメント、透明性の向上が重要な要素となる。
タグボートとしては、「アートを買うこと=資産運用」という考え方だけではなく、「個人の情熱」や「社会貢献の一環」としてアートを楽しむ「推し文化」を育成したいと考えている。アートを購入する喜びや、作品を手元に置く感動をより多くの人々に伝えることで、アートが生活の一部として根付く未来を目指す。
私たちはこれからも、アート市場の課題に正面から向き合い、タグボートとしてその先兵となるべく挑戦を続けていく。