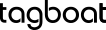アートの価格が上がる仕組み その1
アートの価格とはどのように決まって、どのように上がっていくのかを不思議に思う人は多いであろう。
アートの価格の根拠が分かりにくいのは、特に高額の作品だ。
時間と労力をかけた作品や材料の元値が高い作品であれば、なんとなく価格に対する納得感はあるが、コンセプチュアルな現代アートは価格の根拠がわかりづらい。
とはいうものの、作品の価格には必ず根拠があり、それが上がる仕組みもあるのだ。
まずはアートの価格を決める法則の変遷から見ていこう。
アートの価格は年功序列から人気投票へ
アートの価格は以前は年功序列のような仕組みによって作られていた。
それが、現在では作品の人気度によって作品が上がるセカンダリー主導の仕組みに変わってきている。
作家の略歴、つまり東京藝術大学を頂点とする学歴社会と、公募団体展での入選・入賞回数によるピラミッド階層がメインだった時は、その階層が上がるごとに価格も上がる「号当たり単価」が存在した。
号当たり単価とは、1号(葉書サイズ)で単価が決まり、サイズの号数が上がると価格はその掛け算となっている。
今でも「美術年鑑」のような業者が出版する本には作家別の「号当たり単価」が掲載されているが、実際に売買される価格はその価格を下回ることのほうが多い。
号当たり単価が団体展のヒエラルキーによって作品価格が形成される歴史は、日本独自のシステムで培われてきたものであり、今も画歴が長いだけで重宝されたり、売れる売れないに関わらず価格が高い作家がいる。
ほかの産業でもそうなのだが、このような年功序列が徐々に崩壊していくのは資本主義の流れである。
価値を早く上げたいコレクターやアーティストが存在すれば、それを助長する流れが働くのである。
つまりアートにおける自由な売買市場が存在しなかった時代には、そのような年功序列によって価格が決まることも許されたのだ。
しかしながら、欧米で始まったオークションハウスによる2次流通(セカンダリーマーケット)が日本にも広まることで、初めて共通のモノサシとなるものが発生したのだ。
ここでは、オークションは基本的には需要と供給との交差点によって価格が決まることが前提となっている。
オークションによるセカンダリーマーケットが拡大するにつれ、お金持ちが所有していたお宝品を一部の欲しい人が買うイメージから、自由に売買される市場へと移行していって現在にいたる。
アートの価格形成にはセカンダリーの存在が大きく、プライマリーでギャラリーが売る価格もオークションで取引される価格に一部依存される形となる。
一次マーケットといわれるプライマリー作品は、まだセカンダリーマーケットに出ていない場合はギャラリーがその販売量によって価格を上げるが、次の展覧会までにあまり急激に上げることはしない。
それはそれまで購入してもらったお客様が買えなくなるのを防ぐためでもある。
さて、需要に応じて供給価格が決まるのであれば、需要が落ち込めば価格が下がってしまう場面もあるはずである。
しかし実際にはギャラリーが付ける価格はいまだ年功序列的であり、毎年少しずつ上がることが前提であり価格が下がることはほとんどない。
価格が下がることは作品の評価が下げることを意味しており、作家個人のモチベーションを下げることにもなるので、実際には据え置きはあっても下がることはまずない。
つまり、ギャラリー側がつける価格というのは必ずしも市場を反映しているわけではないということである。
ある意味でセカンダリーマーケットに行くまではどうなるか分からない「お試し価格」なのである。
つまり、ギャラリーでの価格が上がるかどうかは顧客の目利き次第ということだ。

とはいいながら、ギャラリー、特に米国の大手コマーシャルギャラリーについては、セカンダリーマーケットを絡ませながら、必ずと言ってよいほど作品価格を急激に上げてくるのだ。
それは、セカンダリーのマーケット、つまりオークションハウス側と裏でつながっていることを意味する。
もちろん美術館やメディアとも密接な協力関係を作っているのだ。
お互いが結託してアーティストの価格を上げる仕組みを作っているというわけである。
結託されたシンジケートの中にいれば価格が上がる前に早めに作品を手に入れることも可能で、価格を彼らの手によってコントロールすることも可能だ。
これは金融ビジネスであれば、間違いなくインサイダー取引であり、非合法なのであるが、アートの場合は特になんらかの法律で縛られているわけではないというからびっくりだ。
このような一部の人にだけ利益が誘導されるような流れは本来なら公平ではないため、アートが金融と同じような投資のポートフォリオとして今後認知が進んでいけば、そのようなインサイダーを正すためのルールも必要となってくるだろう。
さて、次週ではもう少し詳しくアートの価格が上がる仕組みについて説明したいと思う。