
濱村凌が語る、tagboat art fair に向けた想い。ブースに足を踏み入れた瞬間に、震えさせるような展示がしたい。 -前編ー
同世代を圧倒する分量とスピード感で精力的な活動を繰り広げ、「人が人と関わった時に生じる間」を描き続けてきた濱村凌。2021年3月に開催予定のアートフェア「tagboat art fair」に出展が決まり、10mもの壁を使った広いブースでの展示に向け着実に準備を進めている。今回は人形町オフィスにてタグボートの徳光と寺内も加わりインタビュー企画が実現。濱村凌にとって今年はコロナ禍でありながら成長のー年になったという2020年を振り返り、作品の変化や今後のアーティストとしての目標、そして「tagboat art fair」の展示に向けた想いを語ってもらった。
取材・文=星野 撮影=寺内
人と会えていない状態で、僕が人を描くということに違和感が出てきた
ー濱村さんは今まで人のシルエットをモチーフに扱う作品を多く発表されてきましたが、2020年になってモチーフを使わない抽象的な表現に移行したように感じます。その変化に何か理由はありますか?
まず、僕は抽象を描こうと思って抽象的な表現を用いていないんですね。よく絵を観ていただいた方に「具象ですか、抽象ですか」と聞かれることがあるんですが、僕にとってはそう区別することに違和感があって。具象が 1 だとして抽象が 10 だとすれば、自分がそのときに描きたいものに応じて 6 とか 4 とか、その幅の間でコントロールして表現方法を選んでいるという感覚があります。
そのことを踏まえた上で、なぜ今抽象的な表現に向かっているかというと、今年はコロナ禍によって人と会えなくなったんですね。僕は以前から「人が人と関わった時に生じる間」を描いてきたんですが、今までのように人と会えていない状態で、僕が人を描くということに違和感が出てきたんです。以前にも、「街」を描こうとして結果的に抽象的な表現を用いたこともあったんですが、コロナ禍によって人に会えなくなってからは、より抽象的な表現を扱うようなテーマで描くことが多くなりました。描きたい「人」の何かがたまっていない状態で、アウトプットするのがリアルじゃないという。自分のリアルを考えたら、結果的に、抽象的な表現の作品が増えていったという感じです。
大事にしているのは、それぞれの作品に合わせて言葉を届けること
ーなるほど、日々の中で「人」と関わる時間が作品に大きく影響を与えるんですね。タグボートのECサイトで販売されている濱村さんの作品には、日常の場面を彷彿とさせるような「語り」がテキストとして添えられていますが、そこには何か意図はありますか?
そうですね、僕は色々な場面で「伝える」ということを大事に思っています。
よくバーに行くんですが、バーって接客の仕方が場所によってわかれるんですね。オーセンティックかどうかとか、ショットバーかどうかとか、あとはホテルのバーか、街場かとか。
ー濱村さんは、よくご自身のアーティスト活動をバーのカウンター越しの接客の視点で例えられますよね。これまでに、バーテンダーに救われるようなご経験もあったとお聞きしています。
僕がアーティストとして心掛けている接客の態度は、お客様に寄り添うようなスタイルです。街場のバーに近いですね。
ECサイトの販売でいうと、それぞれの作品に記述するテキストをその作品に合わせて毎回変えるようにしています。制作するときに、毎回考えていることが違うんですよ、バラバラなんです。例えば、赤いりんごというモチーフを描くとなったら、その時その時で黄色を混ぜて使ったり、使わなかったり。毎回そのときに描きたいものを描くので、モチーフからも描きたいところを選び出して描いてるんです。なので、それぞれの作品に合わせてちゃんと説明を届けたほうが、求めてくれる人に届きやすいんじゃないかなって思っています。

ー展示会などで直接お客様とコミュニケーションをとる場合も、「伝える」ということに工夫をされているんですか?
展示会では、文章で伝えるときとはちょっと違うことを意識してますね。というのも、そのときのお客様の状態に合わせて、言葉を少し変えたり、テンポも変えて伝えています。
ーお客様の状態というのは、アートに対する知識の深さの度合いのようなことですか?
アートに対する知識を含む場合もあるんですが、そのお客様が求めるものによる状態が大きいです。癒しが欲しくてきたのか、または刺激が欲しくてきたのか、単純に僕を面白いと思って来てくれたのか。それぞれの状況に合わせて、言葉を変えて伝えることがプロなんじゃないかなってゆう気持ちがあります。
ー作品について「語る」「伝える」ということに、ポリシーを持たれているんですね。
僕、大学生の頃と今を比べて、作品への態度がすごく変わったんです。大学1,2年生のころ、まだタグボートと出会ってないころですね。当時は観る人に丸投げするような作品を描いてたんですよ。例えば、水を題材に作品を描いたとき。僕が伝えたい水の形を描くというより、水ってどうゆう形に観えますか?みたいな描き方だったんですね。水って人によって想像する形が大きく違うじゃないですか。そうゆう作品から伝わるイメージをお客さんに丸投げするような作品を描いてた頃があったんです。
それから、いろんな壁にぶつかったり悩んだり、人生でいろんなことを感じていくうちに、それが嫌になって。僕はアーティストで、何か伝えたいことがあるから描いてる。それなのに、お客様が感じたようにって丸投げして描くのが僕のやりたいこととは違うなと思うようになったんですね。僕は、そのときの「リアルな僕」を160キロの球で投げて、どうだ!ってやりたいんです。
ー抽象画というのは、観る人が想像を自由にしやすいようでいて、とっかかりがないとその先の想像に踏み込みにくい一面がありますよね。濱村さんの「伝える」という意識や行動は、それを手助けしてくれる。作品に添えられている「語り」もその一つなんですね。
日常の中で意識的に言葉をインプットする
(徳光)制作するときは、「語り」と「描く」のどっちが先にあるの?描いたあとに語りが出てくるの?
語りはあとですね。制作して、語りがすぐに出てこないこともいっぱいあるんですよ。一つの作品に添える言葉を考えるとき、一番長い時で一週間くらいかかるんですね。そうゆうときはずっとスタバで悩んでます(笑)ただ、描く前からこうゆうことを伝えたいとか表現したいとか、言葉にはならないけど、”気持ち”はあるんです。それをいざ作品にして、文章くらいの長さの言葉になるのは、作品ができたあとですね。

ー濱村さんの文章は、その作品から想像し得るイメージを押し付けることなく、広がりを促してくれるような絶妙なバランスを感じるんですが、普段から文章を作ることに対して意識していることはありますか?
小説や文学はあまり読まないのですが、日常の中で意識的に言葉をインプットするようにしていますね。ひたすら音楽(Hiphop)を聞いて、そこでどんな言葉や文法、イントネーションで発声されているか気にしたり、CMやドラマでどのシーンにどんなセリフで表現しているかを考えたり。あとはTwitterの140文字という制限の中で、どの職業の人がどんな発信をしているか観察したりします。
ーその中でも印象に残っている言葉の表現はありますか?
僕、90年代に流行った「東京ラブストーリー」が好きなんですね。その第一話で、落ち込んでナーバスになってるカンチに、リカが「8月31日の小学生みたい」と言う場面があるんですよ。落ち込んでいる人に向かって、リカは「落ち込んでるんだね」っていうんじゃなくて、そういう言い方をするんです。それがすごくリカらしいなと思って。ってゆうようなことを僕はすごく気にするんですよ。
例えば「好き」ってゆう言葉を、別の言葉で100通り考えてみる、みたいなことが好きなタイプなんです。

できないことが増えていった2020年。この状況で自分は何ができるのか
ー2020年を振り返って、濱村さんにとって何か変化はありましたか?
まず言っておきたいのが、強くなりました、僕!
ーおー!!!
そう、強くなったんですよ。もう一回言うと(笑)
(徳光・寺内・星野)おー!!!?(笑)
ーどうゆうふうに強くなったんですか?
自分で自分のことをたくましいなと思うようになりました。別に、ナルシストってわけじゃなくて。
(徳光)いや、基本的には濱村さんってナルシストだよね(笑)間違いなく(笑)
え、僕は鏡をいつも見るタイプとかではないんですけどね(笑)
何を言いたいかというと、2020年はコロナ禍によって、できないことが増えたんですよ。まず、海外に行けない。海外に行けないってことは、すごく僕ら作家としては痛手で、そっちでの活動ができないんですよ。ってなると、当然売上にも影響してくる。あとは作品のインスピレーションを得るにも、海外に行ったり、地方にも行けない。できないことが増えていった状況の中で、自分は何ができるのかってゆうのをすごく考えたのが、コロナの時期でした。今も考えてるんですけどね。
で、結果的にどうなったかというと、例えば今年の9月にホテル雅叙園東京に展示させていただいた作品は、自然をモチーフに描いたんですね。今まで僕が自然をモチーフにするときには、地方の自然が豊かなところに行って、スケッチなりして、情報をためることから制作を始めていたんですが、今年は移動自粛のためにそれができなかったんです。そこで何をしたかというと、地方のワインを取り寄せて、テイスティングして、そこから自然を想像するような制作方法に変えたんですよ。ワインって「天地人」っていう考え方があって、天の恵みと土壌と、それを育てる人によって味わいが変わるんですね。モデルとしてワインを採用することで、想像の中で自然にアクセスする。これは、コロナで地方に行けないという状況じゃなければ出てこなかった方法論だと思うんですよ。
 TAGBOAT×百段階段展 展示風景
TAGBOAT×百段階段展 展示風景
ー逆境を活かした発想ですね。
あとは、海外で活動できなかった分、日本での他の業界との関わりをすごく意識するようになりましたね。最近では映画プロデューサーの人と会ったり、ファッションブランドの人とコラボの話があったり、出版社の人との装丁の話とかも来てて。アート業界以外の、日本の業界を見るようになりました。そうすると、アート業界で求められる以外の部分が鍛えられていく感覚があります。そうして、意識的にちゃんと鍛えていき、視野を広げていく。そうゆうことをやっていくことで、作品も変わってくる。そんな循環の繰り返しでした。
ー徳光さんも、今年になって濱村さんの変化を感じますか?
(徳光)コロナが来て変わったというより、コロナの前から準備してたことが、コロナの状況にうまくはまったということも多いんじゃないかと思うんだけど、どうなんだろう?濱村さんの作品って、昨年のタグボートアワードで入選した頃くらいから形が変わっていったじゃない。俺が思ってたのは、具象から抽象に変わった以外にも、色が変わったと思うんだよね。今まではファンタジー感のあるレインボーのような色だったのが、いっきに色合いが落ち着いたよね、言い方は悪いけど、どす黒くなったというか。コロナになってから、その傾向が強くなった気がする。
 TAGBOAT AWARD 展示風景 左から二番目「右手に過去を添えて、今は未来と語ろうか」濱村凌
TAGBOAT AWARD 展示風景 左から二番目「右手に過去を添えて、今は未来と語ろうか」濱村凌
 「右手に過去を添えて、今は未来と語ろうか」濱村凌, 72.7 x 91 cm, 2020
「右手に過去を添えて、今は未来と語ろうか」濱村凌, 72.7 x 91 cm, 2020
そうですね、自分でも作風の変化の傾向は徐々にあったと思います。前のファンタジー感を与えるような作品を描いていたときの自分の気持ちは、誰かを癒したかったんだと思うんです。コロナによって明確に危機を意識するようになって、「ファンタジー」より「リアル」を描きたいという気持ちが自分の中で色濃くでてきた。今は癒すというよりかは、救いを求めるような作品表現になっているのかもしれません。
後編 : 濱村凌が目指すアーティストの姿、2021年3月に控える「tagboat art fair」に向けた想いとは
関連する記事
Category
Pick Up
- 友成哲郎・アーティストインタビュー「人をめぐる欲求のかたち」
- 新埜康平・アトリエインタビュー「二つの文化が交差する新たな日本画の地平」
- 池伊田リュウ・アーティストインタビュー「視界を追い、生命と自然を考える」
- HARUNA SHIKATA・アーティストインタビュー「過去を上書きし、現在を描く」
- 都築まゆ美・アーティストインタビュー「二面性のあいだに揺れる、普遍の物語」
- 月乃カエル・アーティストインタビュー「それでも世界は美しい」
- 石川美奈子・個展アーティストインタビュー「線と色が現象を可視化する。」
- 海岸和輝・個展アーティストインタビュー「色の相互作用から生まれる幾何形態」
- 市川慧・個展アーティストインタビュー「目に見えないものを想像することの大切さ」
- 有村佳奈・個展アーティストインタビュー「本物とは何か、AI時代のリアルを描く。」
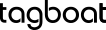
 濱村凌 | Ryo Hamamura
濱村凌 | Ryo Hamamura












