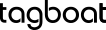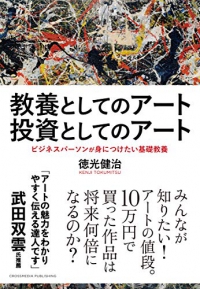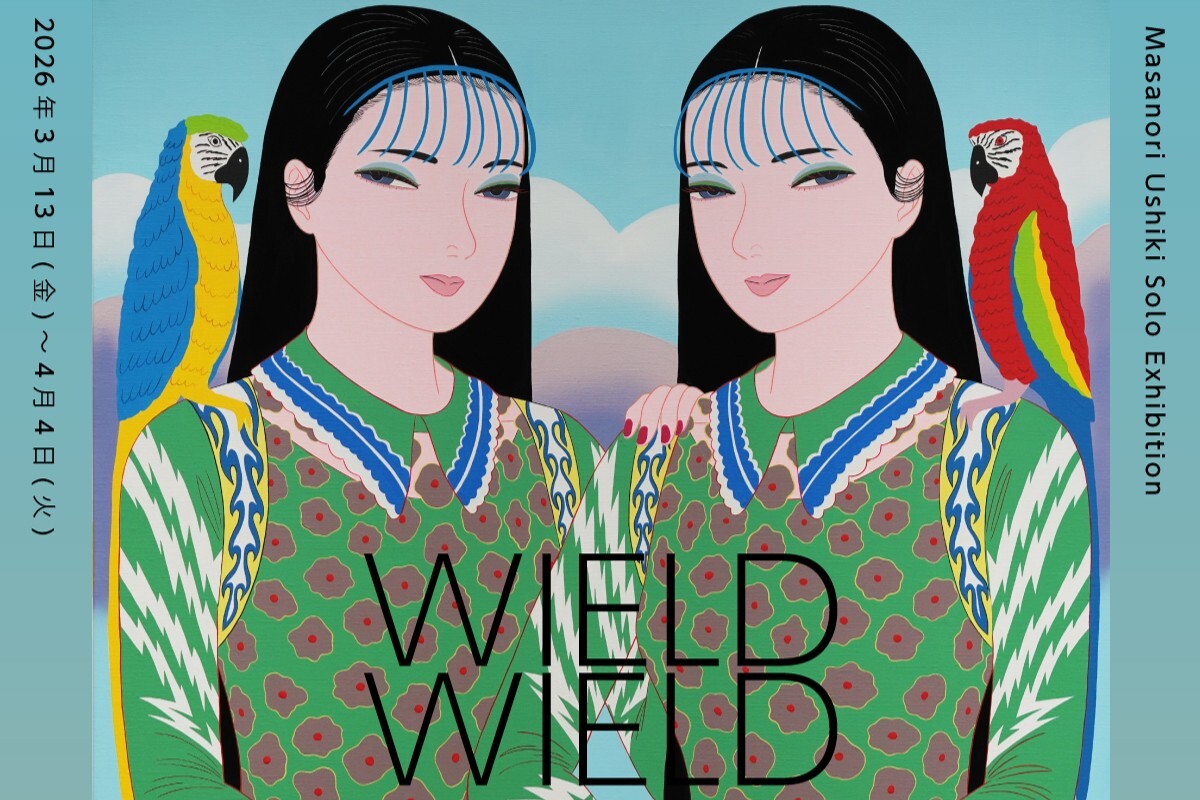人を動かすチカラ──ライブとアートの話
最近では、どんなに配信技術が進んでも「生のライブ」にしかない力が再び注目されている。
たとえば、あるバンドが地方都市でライブを開催したとき、その会場には全国からファンが駆けつけ、チケットは即完売。
グッズ売り場には長い列ができ、SNSには「感動した」「一生の思い出」といった投稿があふれた。
だが、これは単に「いい音楽だった」からではない。
実はそのバンドは、ライブの数か月前からSNSで地道に発信を続けていたのである。
毎週欠かさずリハーサル風景を投稿し、メンバー同士の会話をライブ配信し、今回のツアーへの思いをブログに綴っていた。
それを見た人たちは、だんだんその世界に入り込み、「どうしても現場で観たい」と強く思うようになったのだ。
このように、リアルなイベントが成功するかどうかは「事前のネットでの仕込み」にかかっている。
これはライブだけではない。アートの展覧会でも同じである。
アーティストがただ絵を飾るだけでは、人はなかなか足を運ばない。
SNSやWebでその作品の背景や思いを丁寧に発信し、それを何度も目にすることで、ようやく「見に行こう」という気持ちが芽生える。
ポイントは「時間」と「くり返し」である。
最低でも数か月前から、毎週・毎日といった形で継続的に情報を発信していくことが大事だ。
一度では人の記憶に残らない。でも、何度も見て、耳にして、言葉を聞くことで、らせんのように記憶が定着していく。
そしてもう一つ重要なのが「ストーリー」である。
たとえば、あるアーティストが「どうしてこの作品を描くようになったのか」「なぜこの色を使ったのか」「今どんなことに悩んでいるのか」といった背景を語ると、その作品はただのモノではなく「物語」になる。
人は物語に心を動かされる。これは昔話やアニメが記憶に残りやすいのと同じである。
いまアート業界は厳しい状況にある。
コロナ禍のときは、一時的に「アートバブル」が起きたが、それは旅行や外食ができないからこそ「何か残るものを」としてアートを買った人たちがいたからである。
決して昔からアートに興味があった人たちではない。
だからこそ、これからは「アートに興味がない人たち」にこそ目を向けなければならない。
音楽、ファッション、映画、ゲーム…。他の世界で心を動かされている人たちに、アートの魅力をどう伝えていくかが勝負なのだ。
たとえば、音楽イベントとアート展示を組み合わせたり、人気のあるアパレルブランドとコラボレーションしたりすることで、新しい客層を取り込むことができる。アートを「美術館の中」だけに閉じ込めておく時代ではない。
そして、最も重要なのが「集客力」である。
集客とは「人を動かす力」である。ネットでページが見られた回数(ページビュー)とは違う。
スマホで作品を見ることは簡単だが、実際にその場所に足を運ぶには、心を動かされなければならない。
つまり、「行きたい」と思わせることが、どれだけできるかが問われているのだ。
これはビジネスでも同じである。
お金に変わるのは「人を集める力」であり、それはやがて「ファンをつくる力」につながる。
だからこそ、「人が来ても売れない」と言い訳をするようなギャラリーや販売者は、まず「人をどう動かすか」という基本を見直すべきである。
アートは静かな世界に見えるかもしれない。
でも実は、そこにはたくさんの戦略と努力が詰まっている。
ライブと同じように、何か月も前から準備をして、毎日のように言葉を届けて、やっと誰かの心を動かすことができる。
だからアートに関わる人たちは、もっと発信しよう。
もっと物語を語ろう。そして何度でも届けよう。人が集まる場所には、いつも物語がある。
そしてその物語が、また次の誰かの心を動かしていくのだ。