VIP PREVIEW開催中は会場限定販売となりますので、
VIP PREVIEWにご参加を希望される方は、下記のGoogle Formよりお申込みをお願いいたします。
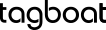

設計図なき手仕事
濱田有美の作品に、スケッチブックというものは登場しない。
どんなに複雑な造形も、頭の中に浮かんだイメージをそのまま手にうつし、粘土で形にしていく。
まるで、風景を見てスケッチする画家ではなく、風を感じたままに即興で踊るダンサーのような創り方である。
このスタイルは、彼女が重んじる「鮮度」のためでもある。
イメージが浮かんだ瞬間がもっとも新鮮で、もっとも自由である。スケッチしてしまえば、その線が呪文のように作品を縛ってしまう。
だから彼女は、思いついた瞬間に粘土を練り、指先でかたちをつくる。その手つきは、まるでその場でいきものを“孵化”させているかのようだ。
「新鮮な魚は、釣ったその場で刺身にするのがいちばんおいしいんです」と、彼女は笑う。
アートと料理が似ているとはよく言われるが、彼女の作品は、特に“仕込み”より“直感”に賭ける料理人のようだ。
見えない材料をつかまえる
濱田の作品は、どれもカラフルで不思議な形をしているが、その裏には意外なほど繊細で独自の技術が隠されている。
まず素材は、樹脂粘土、軽量粘土、透明粘土、アクリル絵具、レジン、ジェルメディウム、そしてニス。
絵具はリキテックス製の中でもとくに発色のよい黒チューブシリーズを愛用しており、粘土と混ぜて自ら「色粘土」を作るのが特徴だ。
造形の第一歩は、ざっくりとした形を軽量粘土で作るところから始まる。
そこから、色を混ぜ込んだ樹脂粘土で肉付けしていく。この時、熱湯を使って粘土をトロトロにし、ホイップクリームのような状態にして使う技法もあるという。
小腹が空いたときは、思わず食べたくなるらしい。
また道具も独創的である。
陶芸用のニードルや羊毛フェルト用の針、0号の細い筆の棒部分、さらには保育園の頃から使っているハサミまで登場する。
プロ用の道具を揃えてもピンとこなかった濱田は、結局、自分の手になじむものを選んだ。
そう、彼女の手元には「プロ仕様」ではなく「自分仕様」の道具が揃っているのだ。
だからこそ、完成した作品を見た人は「これ、何でできてるの?」と聞かずにはいられない。
見たことがない質感、食べ物にも見える色合い、不思議なツヤ。その正体不明の素材感こそが、濱田作品に命を吹き込んでいる。

笑う生きものは旅をする
濱田のアートには、ひとつの哲学がある。それは「さすらい」である。
彼女が生み出す立体作品は「さすらいきもの」と呼ばれている。
ふらふらとどこかをさまよう生き物ではない。むしろ、「自分らしく、あるがままに」生きる存在の象徴である。
この哲学は、作品のテーマにだけでなく、展示場所の選び方にも表れている。
彼女は廃工場や高架下といった、少し“外れた”場所での展示を好む。
そこは、いわば日常のスキマ。人々があまり目を向けない場所にこそ、さすらいきものたちは生まれる。
なぜなら彼女自身が、生活の中の「スキマ」からインスピレーションを得ているからだ。
ほんの数秒の静けさ、机の隅っこ、壁と床のあいだの小さな空間。そこに誰かの気配や気持ちが宿ったとき、いきものが姿を見せる。
そして、いきものたちは旅に出る。
展示会で見た人の心に住みつき、やがて家に連れて帰られ、観葉植物のそばや棚の上で新たな物語を紡ぎはじめる。
彼女は「作品を見ると元気になる」とよく言われるという。
これは偶然ではない。濱田の作品には「笑っていてもいいんだよ」「自分らしくいていいんだよ」という、静かで力強いメッセージが込められているからだ。

あなたの生活にも「スキマ」を
濱田有美の「さすらいきもの」たちは、ただの飾りではない。
暮らしの中にひょいと入り込み、あなたの気持ちを映し出す相棒のような存在になる。
どこか懐かしくて、でも出会ったことのないこのいきものたち──ふとしたスキマに、ひとつ迎えてみてはいかがだろうか。
──彼らがいるだけで、部屋の空気が、あなたの心が、少しだけ自由になる。
 |
濱田 有美Yumi Hamada |
Schedule
Public View
4/19 (sat) 11:00 – 19:00
4/20 (sun) 11:00 – 17:00
|
|
|
|