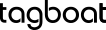アーティストインタビュー 三塚新司|時代と人に寄り添うこと
 |
三塚新司 Shinji Mitsuzuka |
ー美術の道に進むことになったきっかけは?
もともといわゆる天然な人、ズレた人、だったんだと思います。
小学生の頃から絵は描けたので、先生も周りも「絵描きになれば良い」という扱いでしたが、捻くれていたので、言われるままに絵描きになるのは嫌でした。でも絵を描くことは好きでした。
自分は多分、さまざまなことが気になりすぎるというのと、過集中があるので、絵を描いている間は、周りから完全に隔絶されて無心になれる。それが日頃、いろんなノイズで混乱しっぱなしな自分にとって心地よかったんだと思います。

ただ、小中高と、絵を描くのが好き。ということ以上に、人と同じモノを見ても同じコトを感じられていないのがストレスで、それをどうしても矯正したかった。なので高校を出てから6年間、住み込みの仕事を転々としながら、「ズレた自分」を直そうとしました。その為にスキーパトロールやライフガードなど体育会系のバイトをして、殴られながら自分を矯正しようとしました。
だけどそれは結局上手くいかず、自分はどこかズレたままでした。それで24歳の頃に「大学に行って勉強がしたい」と考えて、友人に勉強しないでも入れる大学はどこか聞いたら、彼が「そりゃ芸大の油絵科だよ」と教えてくれたんです。
結局は絵か…とその時諦めて、半年予備校に通って…
それからはすごく急な展開だったのですが、予備校に入って2週間ぐらいで「お前芸大受かるよ」と予備校の先生に言われて、試験会場でも周りの人に「絶対受かりますよ」と言われて、二次試験は芸大の絵画棟で3日間油絵を描いたのですが、お昼に芸大の食堂に行ったら食堂の親父にまで何故か、「お前は受かる」と言われて…それまでの自己評価との変化が大きくて、訳が判らないというのが正直な所でした。
それで芸大に油絵科受験で入って、その年に新設された先端芸術表現科の一期生に編入しました。
合格後に食堂の親父が、「な!受かったろ!数年に一人、こいつは絶対受かるなって奴が判るんだよ!」と言っていました。

その頃からなんとなく感じていたのですが、自分は絵が極端に上手いというより、結局は、人と同じモノを見ても同じコトを感じられていないというのが、違う構成の絵や作品を作らせてくれているんだと思います。
だから何故美術の道に進んだのかというと、結局は他のことが出来なかったからだと思います。他のことをしていたら、多分自分はもっと強烈に壊れていたと思います。
ーそこからどのように作品制作に向かったのでしょうか?
自分にとって作品は結局、社会とか世界という自分の外部から感じたことに対する応答として出力されているんだと思います。

もちろん自分の内側の資源だけで制作に向かう人も居るけれど、自分の場合は、外側で起きていることを、自分の感受性というフィルタで濾し取って、そのフィルタに溜まった澱のようなモノを作品制作の資源としている。それを更に極端に言うならば、「感受性のフィルタを維持する為に定期的にフィルタの汚れを取る」ということでもあるんだと思います。多分、作品を作らなかったら、フィルタが目詰まりして、感受性が折れてしまう。そういう意味で、作品は自動的に作られていくモノでもあると思っています。
ー感受性のフィルタとは?
感受性のフィルタは、それぞれのヒト毎に、テニスのラケットのようなサイズだったり、金魚掬いのポイぐらいの大きさだったり、あるいは野球のバックネットぐらいのサイズだったりと、フレームのサイズが違っていて、さらにフィルタの目の荒さも違っている。どんなにフレームが大きくても、フィルタの目が荒ければニュースで取り上げられるようなことにしか気がつかないだろうし、フレームが小さくても、金魚掬いのポイぐらい目が細かければ、凄く身近の些細な出来事を掬い取ることができる。
感受性のフィルタの目の細かさとフレームの大きさを考えて、自分というフレームが折れないようにする。フィルタが破けないようにする。それが凄く大切なことだと思っています。
だから、テレビ番組の制作などの仕事を辞めて作品を作れるようになった時、生活は大変になったけれど、感受性という意味では本当に楽になった。
自分の感受性が、「今、周辺はこうなっているぞ」「次にこうなるぞ」というように、フィルタに勝手に溜め込んでしまった思い込み、言い換えれば「予測と予測誤差」ですが、それらを掴んで捏ねて形にできる。だから自分は楽になる為に作っていると言えると思います。

そして、その時に思い込みが正しいか正しくないかは多分関係ない。そういう機能を持つ人は一定数居ると思うのですが、結果として、思い込みが時代と合致するヒトと、合致しないヒトと、それぞれどちらもが供給されているんだと思います。
自分は多分、そういう思い込みを持って何かを作る為に供給された壊れたヒトなんだと思っている。そして幸運にも今、作家をしている。
自分にとって「作品制作に向かう」というのは、そういうことだと思っています。
ーそこで作られた作品の意味とは?
そういう意味で作品は、ヒトという種が作ったさまざまなバリエーションの一つとして出力されていると思います。なので、美術の文脈では「誰が作ったか」は重要ですが、ヒトと感受性の関係という意味では「誰が作ったか」は重要では無いと思っています。「その時代の何を象徴して作られたモノなのか」「何に気づいたと思い込んで作られたモノなのか」が重要なのであって、その視点からは、作品は個人が作ったモノではなく、「ヒトが作ったモノ」という大きな枠の中でのバリエーションとして捉えている。
なので、自分の作るモノも、そのようなバリエーションになれると良いなと思っています。
ー最後に付け加えたいことはありますか?
文化という習慣習俗の積み重ねの中に、アートと呼ばれる特異な領域がある訳ですが、その領域は、一部の作家や芸術家だけで生まれるものではないと思っています。アートは、さまざまな事柄に心を寄せ、遠い国の不幸な戦争に心を痛め、その報道の真実性まで深く考える、そのような多くの人々の存在によって支えられている筈だと考えています。
考えること、心配すること、同情すること、寛容であろうとすること、そのようなヒトの情緒との同時代性が感じられる作品を作りたいと考えています。バナナの皮の作品は一生制作をしますが、次の平面作品も同じように一生作れるモノになると思います。期待して待っていて貰いたいと思っています。

 |
三塚新司 Shinji Mitsuzuka |

資本のルールの中に取り込まれた理性が、グローバリズムによる構造変化、複雑化した社会問題、デジタルイノベーションによる情報過多という状況を作り出し、私たちが依拠しなければならない筈の社会共同体という足場を狭めているのではないか、、
もしかすると社会は、私たちの置かれたその状況に対する「疑問」を認知させ にくいように、より狡猾にデザインされ続けているのではないか、そし て共同体を構成する私たちもまた、日常という概念の奥深くへ、「疑問」を 隠滅し、秘匿する共犯関係にあるのではないか、私はその疑いを「疑問の 疑問」、「META 疑問」と呼んでいる。
私はそのような「疑問」を元に作品を作っている。
東京藝術大学卒、同大大学院中退。2018年より作品発表を始める。
2018年 池袋アートギャザリング IAG AWARDS 2018 準IAG賞受賞
2018年 Independent Tokyo 2018 入賞 審査員特別賞受賞
2019年 スパイラル SICF20
2020年 公募展 UNKNOWN ASIA 2020 審査員賞受賞
2021年 神奈川県美術展 県議会議長賞受賞
2021年 スパイラル SICF22
2022年 岡本太郎現代芸術賞展 岡本敏子賞受賞
関連する記事
Category
Pick Up
- 友成哲郎・アーティストインタビュー「人をめぐる欲求のかたち」
- 新埜康平・アトリエインタビュー「二つの文化が交差する新たな日本画の地平」
- 池伊田リュウ・アーティストインタビュー「視界を追い、生命と自然を考える」
- HARUNA SHIKATA・アーティストインタビュー「過去を上書きし、現在を描く」
- 都築まゆ美・アーティストインタビュー「二面性のあいだに揺れる、普遍の物語」
- 月乃カエル・アーティストインタビュー「それでも世界は美しい」
- 石川美奈子・個展アーティストインタビュー「線と色が現象を可視化する。」
- 海岸和輝・個展アーティストインタビュー「色の相互作用から生まれる幾何形態」
- 市川慧・個展アーティストインタビュー「目に見えないものを想像することの大切さ」
- 有村佳奈・個展アーティストインタビュー「本物とは何か、AI時代のリアルを描く。」