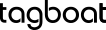有村佳奈・個展アーティストインタビュー「本物とは何か、AI時代のリアルを描く。」
女子美術大学デザイン学科を卒業後、「ウサギの仮面を被った乙女」を主題に、匿名性と自己表現が交錯する現代の姿を描いてきた有村佳奈。仮面は夢の世界への入口から、現代を生き抜くためのアイコンへと変化し、愛らしさと強さが同居する彼女たちの姿を通して、“今”を生きる私たちのリアルを映し出しています。
今回のインタビューでは、タグボートでの個展「Real」に込めた思いや、AIやSNSによって変容する“リアル”の捉え方、そしてこれからの創作への展望についてお話を伺いました。
有村佳奈 Kana Arimura
1985年 鹿児島県出身
2008年 女子美術大学 卒業
展示歴
2024年 個展「Sakura」(Gallery Joyana/パリ)
2024年 個展「CHANGE」(tagboat/東京)
2024年 グループ展「つなぐーTSUNAGUー」(外琨塔 Vaikuntha 藝術中心 /台北)
2017年からウサギの仮面をつけた女性をモチーフにした絵を中心に描き、『現代を生きる乙女の生と死』の表現に取り組んでいる。2023年は女優/ソロシンガー・田村芽実との展覧会「未完成のエピローグ」(EARTH+GALLERY)を開催し、写真・デジタルコラージュ作品等新たな試みにも挑戦。また2024年4月にパリでの初個展が開催、12月に台北での展覧会に参加等、海外での活動の場が広がっている。2024年に女子美奨励賞を受賞。その他、本の装画等のイラストレーションも行う。
本物とは何か、AI時代のリアルを描く。
今回の個展タイトル「Real」には、どのような経緯で辿り着いたのでしょうか?
今回の個展タイトル「Real」に至ったきっかけは、SNSで目にした“企業が生成AIによるイラストを使用したことによる炎上”でした。「有名企業が安易にAIを使うなんて」「元のイラストを無断で引用している」といった批判が多く見られましたが、私が特に印象に残ったのは、「手の描写が不自然だ。人間の絵師ならこんなふうには描かない」というコメントでした。
つまり、多くの人が“本物かどうか”を見分ける基準を「絵の完璧さ」に置いていたのです。けれども、その“完璧さ”こそ、いずれAIが最も得意とする領域になるだろうと感じました。実際、この炎上が起きた2025年6月からわずか数ヶ月後には、新モデル「sora2」が登場し、生成精度は驚くほど向上しています。もはや“AIの不自然さ”で真偽を判断できる時代ではなくなりつつあります。今後、私たちは常に“本物かどうか”を疑いながらメディアと向き合うことが当たり前になるかもしれません。
同時に私が強く感じたのは、“完璧であること”を求める風潮への違和感でした。
「完璧さ」とは何か、「本物らしさ」とは何か――。私自身、作品制作の中で「完璧に仕上げなければならない」という呪縛のような感覚を抱えています。しかし、その精密さを突き詰めるほど、AI的な再現性に近づいていくような不思議な感覚にも苛まれました。
だからこそ一度立ち止まり、自分にとっての“リアル”とは何なのかを見つめ直す必要があると感じました。この問いを出発点に据えたことが、個展タイトル「Real」へとつながっています。

AIやSNSの普及による“リアル”の変化をコンセプトに掲げていますが、作品制作のプロセスを教えてください。
今回の個展では、作品を3つのテーマに分けて展開しています。
1. 僕らのリアル
TikTokには、写真を瞬時に美しい動画へと変換してくれる多くのエフェクトがあります。その中でも「AI Flower effect」は、風景を一面の花で覆い、“映える世界”をわずか数十秒で生成してしまう機能です。
このエフェクトを初めて見たとき、私は不思議な感情に包まれました。というのも、2020年のコロナ禍で外出が制限されていた頃、私は「花園に包まれた乙女たち」というシリーズを描いていたからです。閉塞感の中で「絵の中では自由に、華やかな気持ちになってほしい」と願い、ロケハンからモデル撮影、下絵の構成まで、丁寧に時間をかけて制作していました。
AIエフェクトと私の作品は手法も意図も異なりますが、「現実を美しく見せたい」という根源的な欲求は共通しています。だからこそ、“手軽に変化できる”ことへの違和感、ある種の“悔しさ”のような気持ちが生まれました。そこで今回は、あえて「手軽ではない方法」で挑みました。
『僕らのリアル』というシリーズでは、渋谷の街に佇む乙女の背景が花へと変化していく様子を、動画ではなく絵画の連作として表現しています。アニメーションの原画のように、時間の流れそのものを絵で描き出しました(M60号2点・M6号6点構成)。現代社会は“タイパ(時間効率)”が重視され、あらゆるものがスピード化しています。しかし、その速さの先に何があるのか、誰も明確には見えていません。だからこそ、私は“時間をかけること”の意味を改めて考えながら、一枚一枚に想いを込めて制作しました。

2. パラレルな私たち
「パラレル私」という作品では、異なるタッチで描かれた複数の乙女が一枚の中に存在します。年齢を重ねるごとに“新しい私”へ成長していくというより、むしろ「5歳の私」「20歳の私」「30歳の私」がすべて内側に積み重なっていくような感覚を表現しています。
現代ではSNSを通して人格が分岐し、「推し活アカウント」「仕事用」「子育て用」など、複数の“私”を同時に生きる時代になりました。XやThreadsのようなテキスト中心のSNSでは、年齢や立場の境界がより曖昧になり、アカウントごとにまったく異なる人生を送っているようにも感じます。その現象が私たちの心やアイデンティティにどんな影響を与えているのか——その問いを、異なるタッチの乙女たちを通して描きました。

3. 大切にしたい今
これからの社会では、“フェイクとリアル”の境界がますます曖昧になっていくでしょう。それでも、スマホの画面を離れ、目の前の人と向き合う時間こそ、私にとって最も大切な“リアル”です。日々の中で小さな幸福を丁寧に感じ取る友人をモデルに、「いま、この瞬間」を慈しむ気持ちを描きました。

制作のインスピレーション源は、どんな日常から生まれることが多いですか?
私は常に「いま自分が何に心を揺らしているか」に意識を向けています。
すべてのニュースや情報に敏感になりすぎると、情報の渦に飲み込まれてしまう。だからこそ、流れる日常の中で感じる「あれ?」という小さな違和感を大切にしています。
その“あれ?”という感情こそ、私のインスピレーションの源になっています。

「リアル」を探求する過程で印象的だった気づきはありますか?
『僕らのリアル』を制作している途中、私生活でさまざまな感情の揺れがあり、描き始めた時と描き終えた時では、作品に込める感情がまったく違っていました。その変化こそ、時間をかけて描くからこそ得られる発見だと感じます。
また、ユヴァル・ノア・ハラリの『サピエンス全史』にある「文化は一種の精神的感染症あるいは寄生体で、人間は図らずもその宿主になっている。ウイルスのような有機寄生体は、宿主の体内で生きる。それらは増殖し、一人の宿主から別の宿主と広がり、宿主に頼って生き、宿主を弱らせ、時には殺しさえする。」という一節がありますが、SNSはまさに“寄生体”のように私たちの思考に入り込み、やめられない存在になっています。
そして今、新たな“寄生体”としてAIが加わり、進化のスピードは加速しています。
その変化に、心が追いつけない人も増えているように思います。
そんな時代だからこそ、「アートは処方箋になり得るのではないか」と考えるようになりました。すぐに理解できるものばかりが求められる時代にあって、“わかりにくさ”はむしろ脳を休ませる作用を持つのではないか。効率や即時性が重視される今だからこそ、アートの持つ“立ち止まる力”が、社会に必要とされていると感じています。

モモコグミカンパニーさんとのトークイベントが予定されていますが、過去に装丁を手がけたときの思い出や、対談ではどんなお話をされる予定か教えてください。
2022年に、モモコグミカンパニーさんの小説『御伽の国のみくる』(河出書房新社)の装丁を担当しました。当時はBiSHの活動で多忙な時期にもかかわらず、一冊の小説を書き上げていたと聞き、その創作エネルギーに深く感銘を受けました。
モモコさんは、音楽・歌詞・エッセイ・小説と、常に“言葉”を軸に表現を続けているアーティストです。絶え間なく発表を重ねるその姿勢には、表現者として心から尊敬しています。今回、自費出版された『氷の溶ける音』をもとに展覧会「言葉をひろう」を開催されると伺い、2012年に私が訪れたドイツの国際美術展「ドクメンタ」で印象的だった“言葉と空間が呼応する表現”を思い出しました。彼女の作品には、まさに“いまを生きる感情”をリアルに掬い取る強い力があると感じています。
個人的にトークイベントで聞いてみたいと思っているのは、モモコさんの大学卒業論文のテーマだったという「アイドルと演じること 〜 一人の人間に見る虚像と偶像〜」のお話です。この論文にすごく興味が惹かれています。ぜひ読んでみたい。
SNS登場以前、テレビというメディアの中でアイドルや芸能人が基本的には、“演じる存在”でした。しかし、SNSが生活の中心となった現代では、多くの人が自らを“演出”し、“映える自分”を日常的に発信するようになりました。「演じること」は、いまや一部の表現者だけでなく、誰もが無意識に行う行為になっていると感じます。
そんな時代に、モモコさんが「BiSH」の活動を通して、“虚像と偶像”をどう見つめ、どんな感情を抱いていたのか。そして解散後、精力的に活動している原動力はどこから生まれているのか――。その核心を、ぜひ直接うかがってみたいと思っています。

お客様の反応が制作に影響することはありますか?
とてもあります。
自分の表現がどう受け止められているかを知ることは、次の制作への大きなモチベーションになります。「応援してくれている人が一人でもいる」と感じた瞬間に、また頑張ろうと思えるんです。そして観てくれる方に「次はどんな作品だろう」とワクワクしてもらえるよう、常に新しい挑戦を続けています。

今後挑戦したいことや展望を教えてください。
先ほど「アートはわかりやすくないからこそ、現代の薬になり得る」という話をしましたが、一方で現代のアート業界は、観る人に“わかりやすく伝える努力”を怠ってきた面もあると感じています。作品に“わかりにくさ”があること自体は悪いことではありませんが、その世界へ入っていくための道筋――いわばガイドラインを提示することは、今後ますます重要になると思います。
私自身もこれまで「作品を作って終わり」という姿勢が多かったのですが、もっとアートへの入り口を広げていきたいと考え、今回の個展をきっかけにYouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@KanaArimura)を始めました。作品の制作プロセスや思考の流れを可視化し、アートの背景にあるリアルな部分を共有していく予定です。
また、今回の展示では小説・エッセイ・詩をまとめた書籍も制作しました。絵画だけでなく、言葉を通して自分の“リアル”を伝えることも、私にとって大切な表現のひとつになっていくと考えています。
課題が見えるたびに新しい挑戦が増えていきますが、それこそが創作の楽しさだと思います。今後も、一つひとつの試みを丁寧に積み重ねながら、アートと社会をつなぐ表現を続けていきたいです。
10月31日(金)からギャラリーにて個展「Real」を開催いたします!
有村佳奈「Real」
2025年10月31日(金) ~ 11月18日(火)
営業時間:11:00-19:00 休廊:日月祝
※初日の10月31日(金)は17:00オープンとなります。
※オープニングレセプション:10月31日(金)18:00-20:00
入場無料・予約不要
会場:tagboat 〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町7-1 ザ・パークレックス人形町 1F
関連する記事
Category
Pick Up
- 友成哲郎・アーティストインタビュー「人をめぐる欲求のかたち」
- 新埜康平・アトリエインタビュー「二つの文化が交差する新たな日本画の地平」
- 池伊田リュウ・アーティストインタビュー「視界を追い、生命と自然を考える」
- HARUNA SHIKATA・アーティストインタビュー「過去を上書きし、現在を描く」
- 都築まゆ美・アーティストインタビュー「二面性のあいだに揺れる、普遍の物語」
- 月乃カエル・アーティストインタビュー「それでも世界は美しい」
- 石川美奈子・個展アーティストインタビュー「線と色が現象を可視化する。」
- 海岸和輝・個展アーティストインタビュー「色の相互作用から生まれる幾何形態」
- 市川慧・個展アーティストインタビュー「目に見えないものを想像することの大切さ」
- 有村佳奈・個展アーティストインタビュー「本物とは何か、AI時代のリアルを描く。」